この時期になるとスーパーで見かける梅。
今年は初めて梅干しづくりに挑戦することにしました!
梅を使った保存食を作ることを、「梅仕事」ということを知りました。素敵な言葉ですね!

はじめての梅しごと!
はじめての梅しごと
調べてみると、梅干しづくりには青梅ではなく完熟梅が向いているとのこと。
スーパーで見かけるのは青梅が多かったのですが、比較的黄色い梅が多い袋を見つけたので買ってみました。1kg入りです。




深さ2~3mmで乾いた傷のものは、梅干しにしても問題ないそうです。
ほとんどを梅干し用にすることができました。
傷の深いものは、傷を切り取って梅みそにすることにしました。
梅干しづくり
まずは梅干しづくりです。塩分10%でつけることにしました!
赤しそは使わないことにしました。
必要なものを用意する
- 梅
- 塩 (精製塩ではなくあらじおが良い)
- ホワイトリカー (アルコール25%以上のもの)
- ビン (フリーザーバッグでもよい)
- 竹串
- はかり
- ペーパータオル


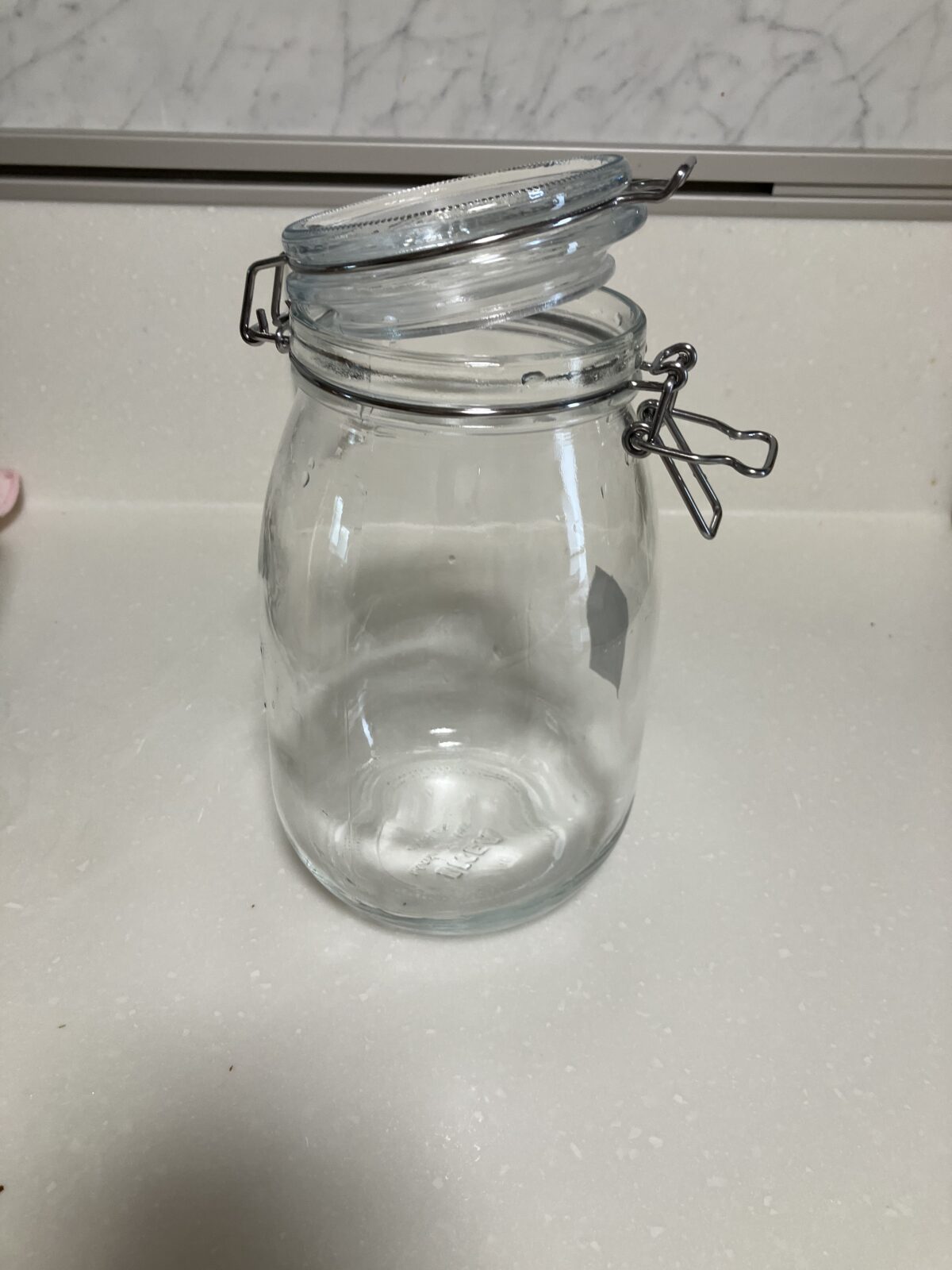
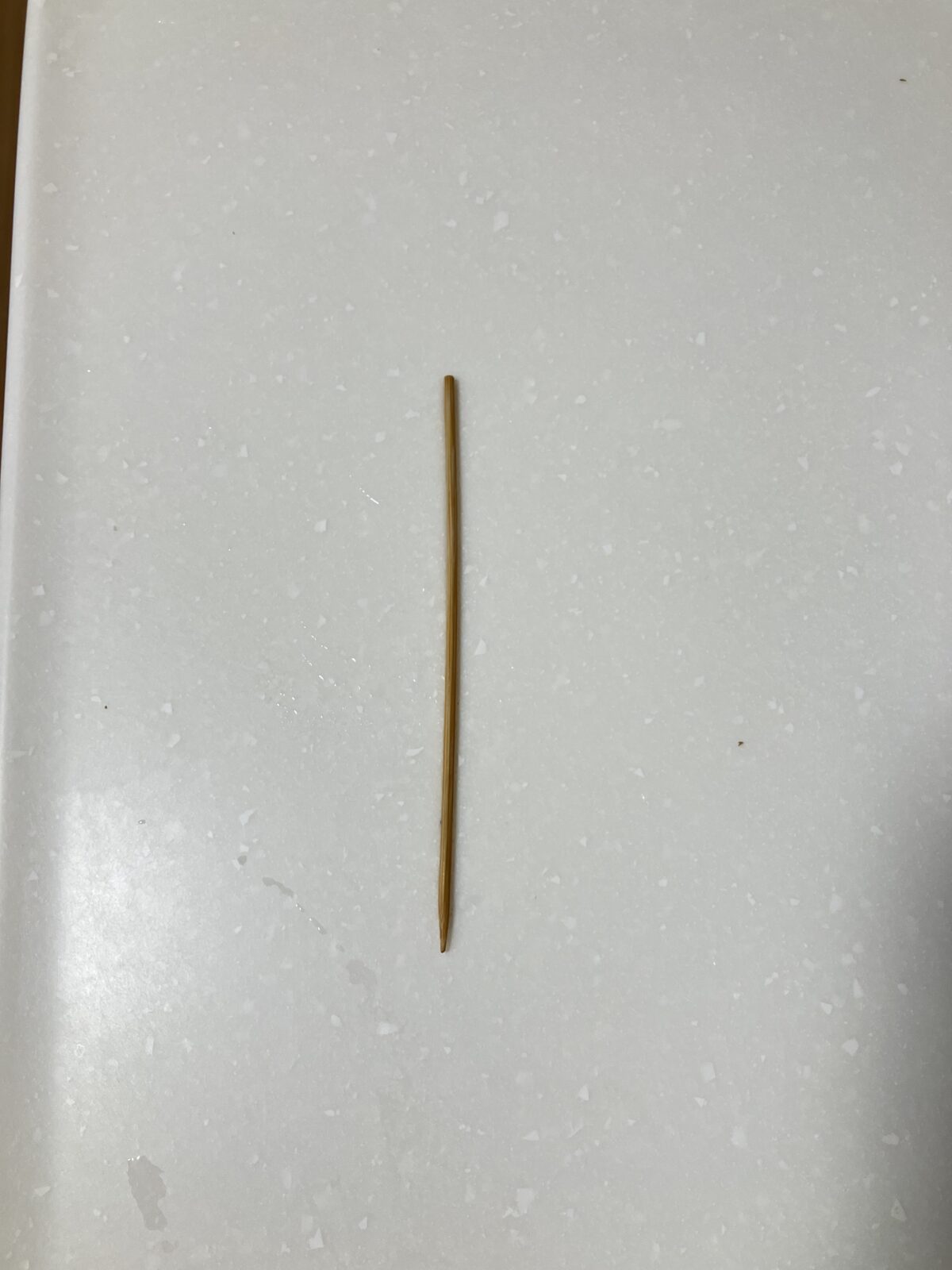
梅の重さをはかる
傷が大きくないものの梅の重さをはかってみると、860gでした!
あとで塩をはかるので、この重さを覚えておきます。
梅を洗って水気を取る
梅を洗ってペーパータオルで1つ1つ丁寧に水気を拭き取ります。おしりのくぼみに水が溜まりやすい
ので、しっかり拭きます。
へたを取る
竹串でおしりのヘタを取ります。


青梅を冷凍する
青梅は、そのままでは固くて梅酢が出にくいそうなので、フリーザーバッグに入れて冷凍します。
1日冷凍しておきました。
その間、完熟梅の方はざるに並べて自然乾燥させておきます。

完熟梅は、甘くていい香りがする!
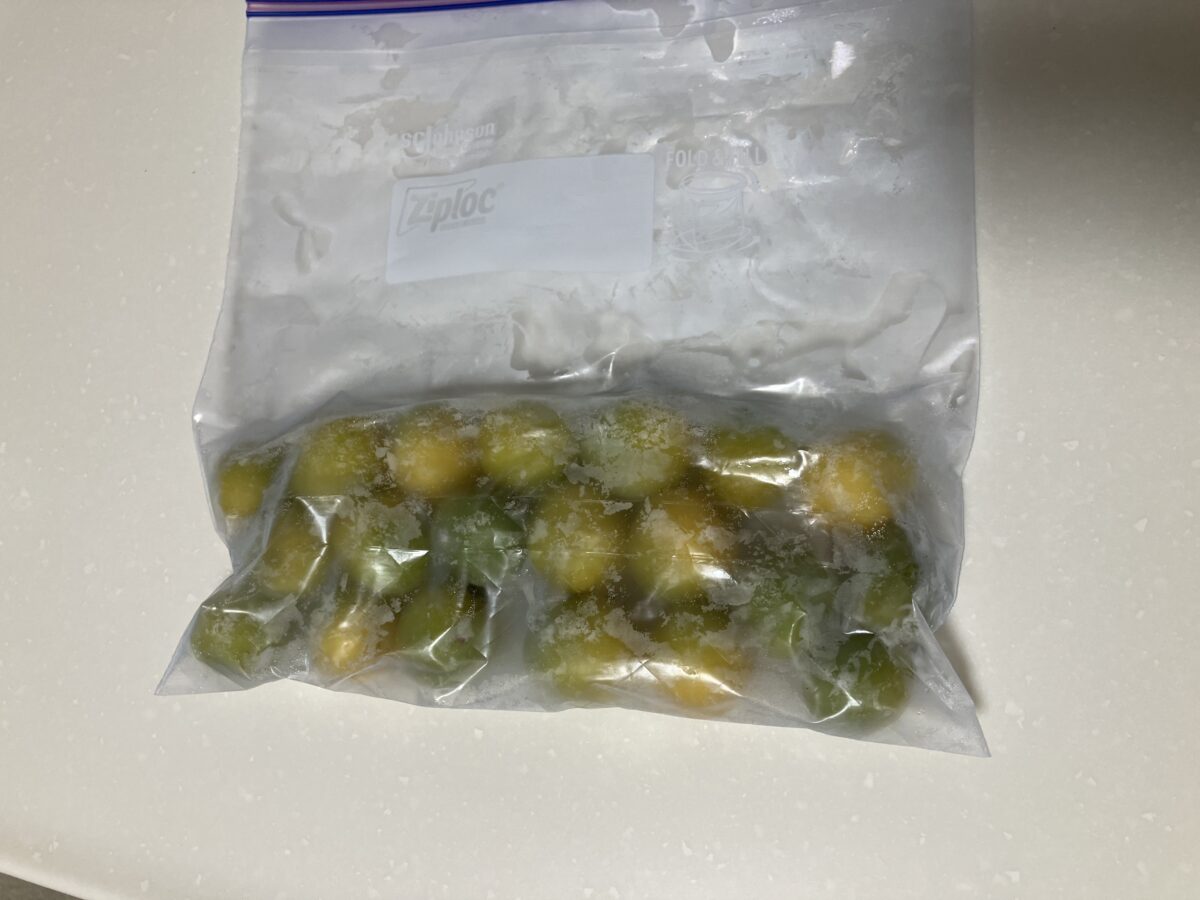
こちらも漬ける前に、ペーパータオルで水気を拭いておきます。
ビンを消毒する
ホワイトリカーでビンを消毒します。
ビンに少量のホワイトリカーを入れて、満遍なくいきわたるようにビンを振ります。
ふたは、ホワイトリカーをしみこませたペーパータオルで拭きます。
消毒したところは触らないように気を付けて、ふたを開けて自然乾燥させます。
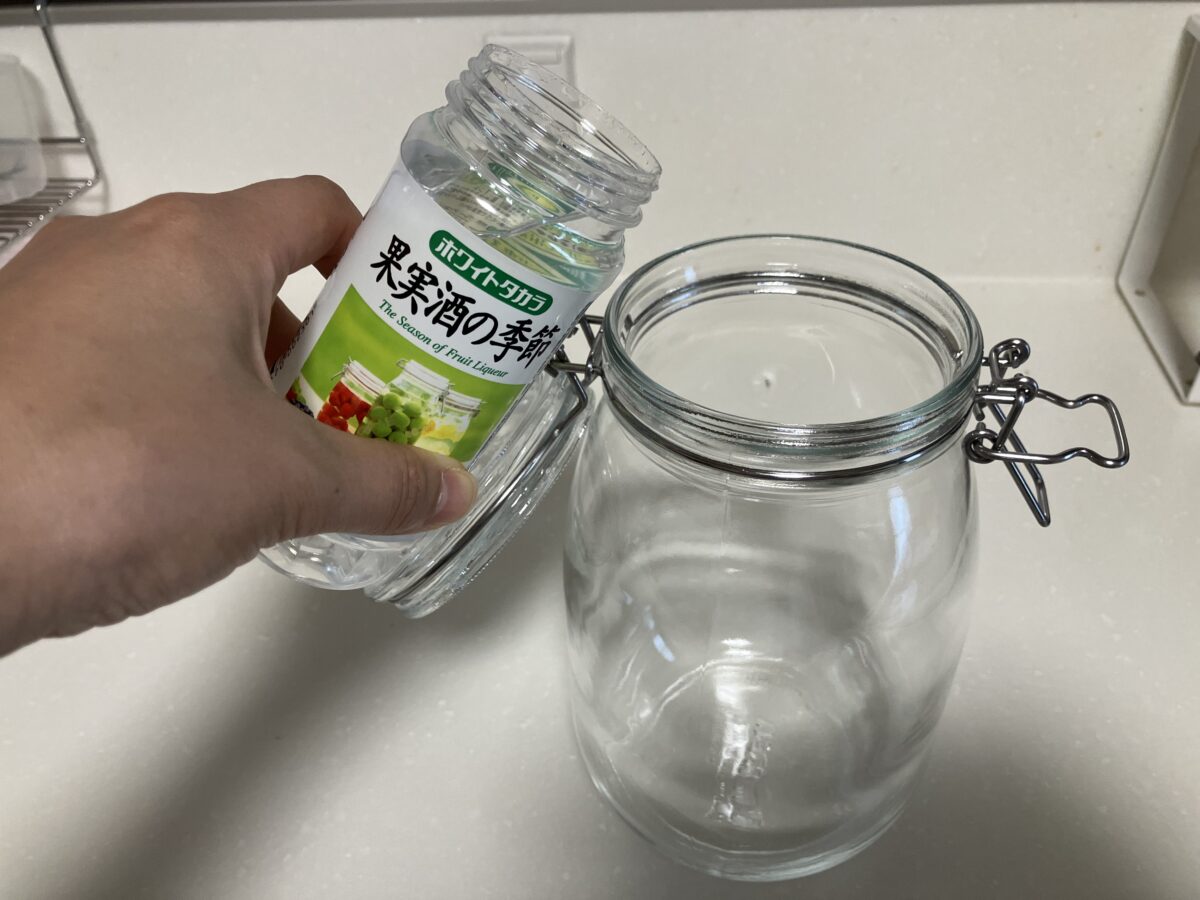

塩を量る
1で量った梅から塩の量を計算します。
860g × 0.1 = 86g
塩を86g量りました。

塩と梅を交互にビンに入れていく
ビンが乾いてから、塩と梅を入れていきます。
初めに塩を入れます。次に梅を入れ、塩を入れて、梅、塩、梅……と重ねていきます。
冷凍した青梅を先に入れ、完熟梅を上の方に入れました。
入れ終わったら蓋をして、このまま30分おきます。


塩漬けだ!かわいい!
ビンを振る
30分たったら、塩が満遍なく梅にいきわたるようにビンを振ります。
マスキングテープなどで日付を書いておくとわかりやすいです。


毎日ビンを振る
毎日4~5回ビンを振って、梅酢が上がってくるのを待ちます!

梅酢が出てきました。
梅酢が出るときに一緒にガスが出るため、時々蓋を一瞬開けてガス抜きした方がいいです。
梅がひたるくらい梅酢が出てきたら、梅雨が明けるまで冷暗所に置いておきます。
梅みそづくり
次に、傷の大きかった梅を梅みそにしていきます。
必要なものを用意する
- 梅
- 味噌 (お好みのもの)
- 砂糖
- タッパ (密封できるもの)
梅を用意する
梅干しと同じように、梅を洗ってヘタを取ります。
傷の部分を包丁で切り落とします。


梅の重さをはかる
傷んだ部分を落としたら、重さをはかります。


134g!
タッパを消毒する
ホワイトリカーでタッパを消毒します。
タッパに少量のホワイトリカーを入れて、満遍なくいきわたるようにタッパを振ります。
ふたは、ホワイトリカーをしみこませたペーパータオルで拭きます。
消毒したところは触らないように気を付けて、ふたを開けて自然乾燥させます。
味噌と砂糖をはかる
梅と同量の味噌、半量(~お好み)の砂糖をはかります。
梅が134gだったので、味噌134g、砂糖70gを用意しました。

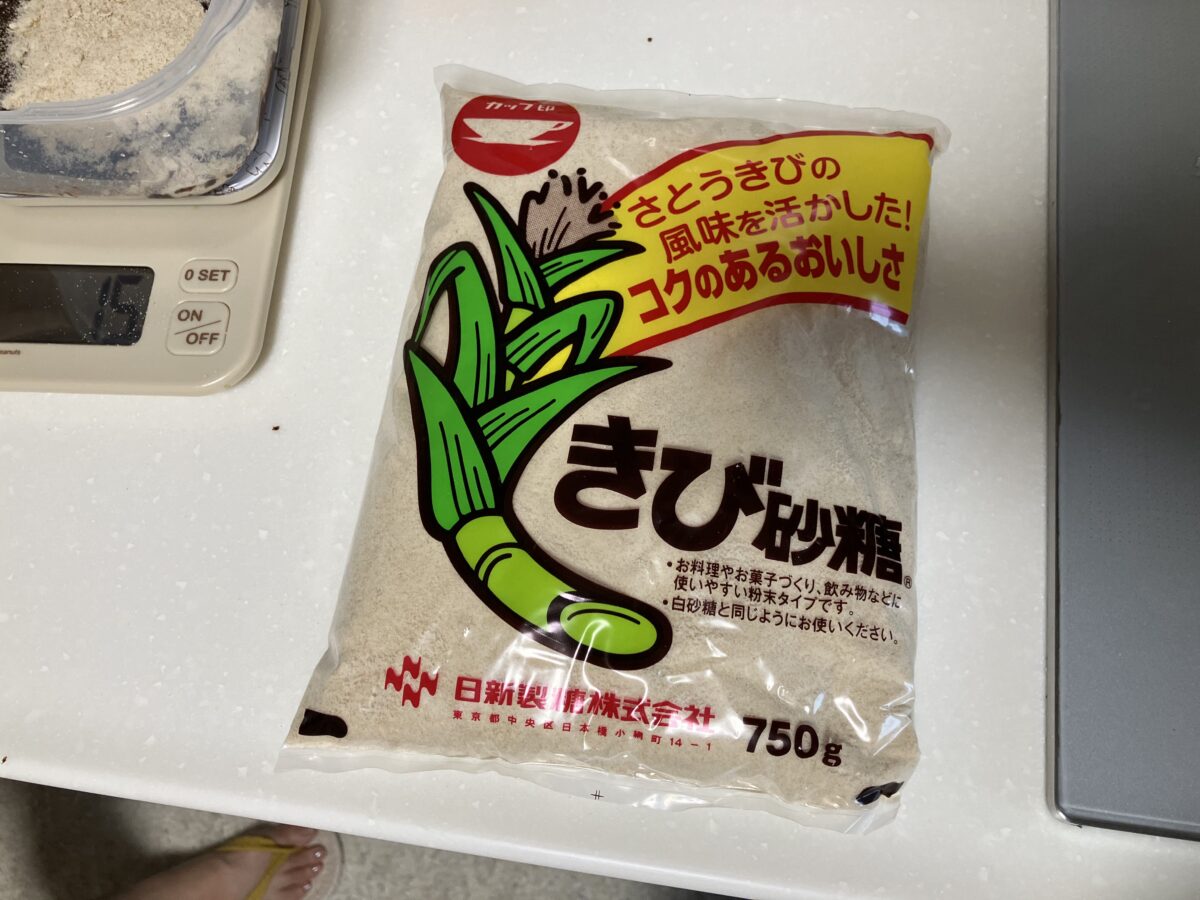
タッパに重ねていく
タッパが乾いたら、半量の味噌、半量の砂糖、梅、半量の砂糖、半量の味噌の順に重ねていきます。
最後は空気に触れないように、ラップをはりつけます。

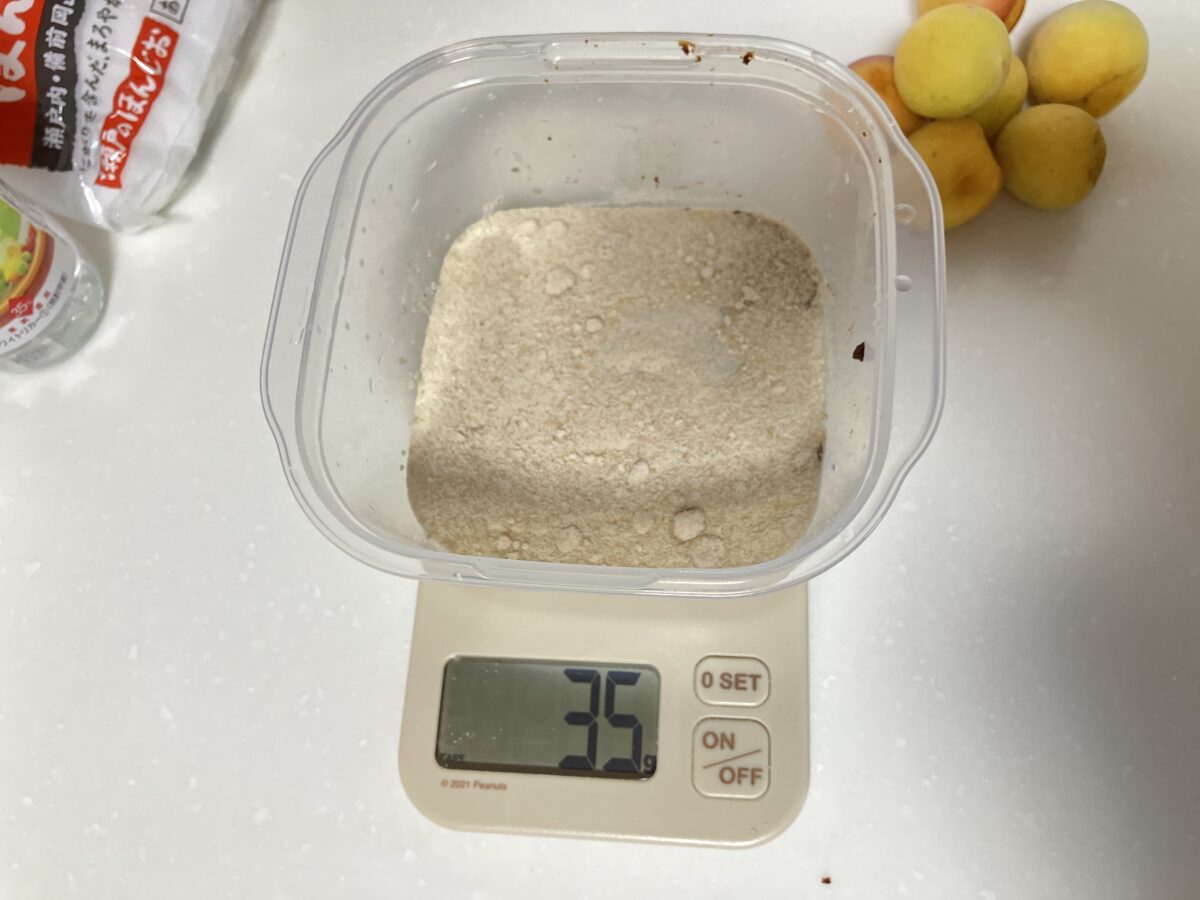

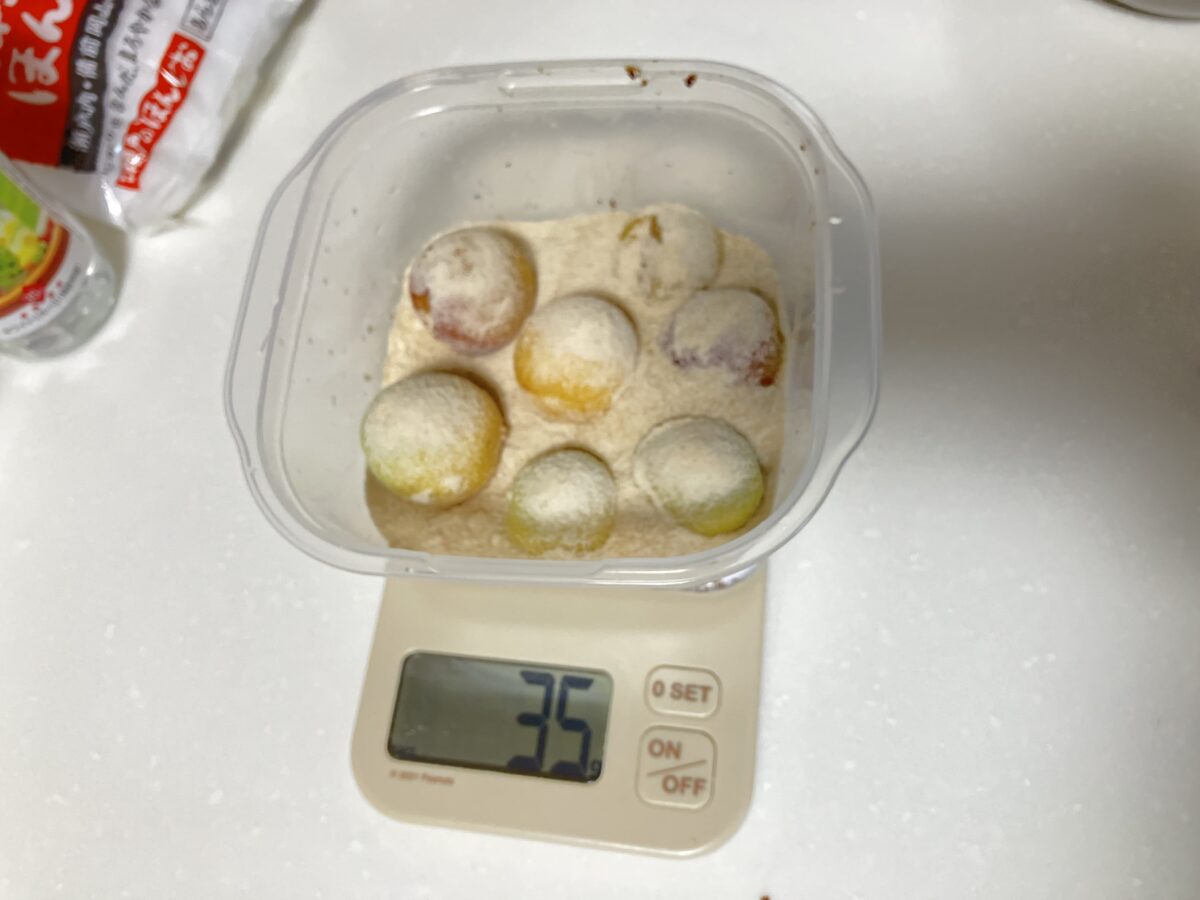



冷蔵庫で保存、時々かきまぜる
冷蔵庫で1か月ほどおき、梅から水が出て味噌がゆるくなったら消毒したスプーンでかき混ぜてラップをし直す。以降は、さらにゆるくなっていたらかき混ぜる。
2~3か月漬けたら完成!
2~3か月たったら食べられるそうです。
はじめての梅仕事、ひと段落しました!
どんな梅干し、梅みそができるか楽しみです!



コメント